近年は自宅をオール電化にしたり、オール電化物件を選んだりする家庭が増えています。
しかし電気代の高騰により「思っていたより電気代が高い」「冬場の請求額に驚いた」という声をよく耳にするようになりました。
特に寒冷地では冬の電気代が月に10万円を超えるケースも報告されています。このような状況に不安を感じている方も多いでしょう。
本記事ではオール電化住宅の電気代の実態や高額になる原因を解説し、効果的な節約方法や適切な電力会社の選び方まで詳しく紹介します。
これからオール電化住宅への引っ越しを検討している方も、すでにお住まいの方も、電気代の負担を軽減するヒントが見つかるはずです。
なお、以下では東京都で太陽光発電の導入を検討している方に向けて当メディアおすすめの施工会社を紹介していますので、ぜひ一度チェックしてみてください。
オール電化住宅とは?
オール電化住宅は、家庭で使用するエネルギーを電気のみでまかなう住宅のことです。
従来の住宅ではガスを併用することが一般的でしたが、オール電化住宅ではキッチンや給湯、暖房に至るまですべてを電気で賄います。
主な設備には、エコキュート(ヒートポンプ給湯器)やIHクッキングヒーター、床暖房システム、蓄熱暖房機などがあります。
オール電化住宅の多くは夜間電力の料金が安い電気料金プランと組み合わせて使用されることで、光熱費の節約が期待できる仕組みになっているのです。
2000年代から急速に普及し始め、新築マンションやリフォーム物件でも採用されるケースが増えてきました。
オール電化の電気代はいくらかかる?

オール電化住宅の電気代は、世帯人数や地域、季節によって大きく変動します。
一般的な住宅と比較すると電気使用量は多くなる傾向にあるものの、ガス代が不要になるため、総合的な光熱費で考える必要があります。
オール電化住宅の電気代に影響を与える主な要素を見ていきましょう。
以下で、詳しく解説します。
世帯人数別の平均電気代
オール電化住宅の電気代は世帯人数によって大きく異なります。
関西電力の調査データによると、オール電化住宅における世帯人数別の平均電気代は以下のとおりです。
| 世帯人数 | オール電化住宅の電気代(月平均) |
|---|---|
| 1人暮らし | 10,777円 |
| 2人家族 | 13,406円 |
| 3人家族 | 14,835円 |
| 4人以上 | 16,533円 |
これに対して、ガス併用一般住宅の光熱費は1人世帯で約10,000円、2人世帯で約16,000円となっています。
この比較から、2人以上の世帯ではオール電化のほうが光熱費の合計が安くなる傾向が見られるでしょう。
季節で変わる電気代
オール電化住宅の電気代は季節によって大きく変動します。特に冬場は電気代が急増する傾向にあるのです。
総務省統計局の2023年家計調査における2人以上の世帯の四半期別電気・ガス代は以下のようになっています。
| 時期 | 電気代 | ガス代 | 電気+ガス代 |
|---|---|---|---|
| 1~3月(冬) | 17,723円 | 8,051円 | 25,774円 |
| 4~6月(春) | 11,354円 | 5,766円 | 17,120円 |
| 7~9月(夏) | 9,885円 | 3,352円 | 13,237円 |
| 10~12月(秋) | 10,099円 | 3,667円 | 13,766円 |
この統計はオール電化住宅に限ったものではありませんが、季節による変動の傾向はオール電化住宅でも同様です。
1〜3月の冬季は他の季節と比較して電気代が最大で約1.8倍に跳ね上がっています。この原因は主に暖房の使用と、エコキュートなどの給湯設備の効率低下にあります。
冬は外気温が低いため、水を温めるのにより多くのエネルギーが必要となり、結果として電気代が高くなるのです。
オール電化住宅のメリット・デメリット

オール電化住宅には、多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。そのため、導入を検討する際は両方の側面を正しく理解することが重要です。
具体的には、以下のポイントを押さえておきましょう。
オール電化の導入が適しているかどうかは、家族構成やライフスタイル、住んでいる地域の特性などによって異なります。それらを総合的に考えた上で判断するとよいでしょう。
オール電化のメリット
オール電化住宅には多くの魅力的な特徴がありますが、第一に、ガス料金がかからない点が大きな経済的メリットです。
電気代は増えますが、総合的な光熱費としては、電気とガスを併用するよりも安くなる傾向があります。
次に安全性の高さも重要なポイントです。ガスを使用しないため、ガス漏れや不完全燃焼による一酸化炭素中毒のリスクがありません。
また、IHクッキングヒーターは炎が出ないため、火災のリスクも低減されます。特に小さなお子様がいる家庭では、この安全性は大きな魅力となるでしょう。
加えて、災害時の復旧も電気のほうがガスよりも早い傾向があります。一般的に、災害時のライフラインの復旧は「電気→水道→ガス」の順で進められるからです。また、エコキュートのタンク内の水は災害時の備えとなる水としても活用できます。
オール電化のデメリット
オール電化住宅には注意すべき点もいくつかあり、最も重要な欠点は、停電時の脆弱性です。
オール電化住宅では停電が発生すると、給湯器やIHクッキングヒーターなどすべての設備が使えなくなるため、長時間の停電に備えて、カセットコンロやポータブル電源などを用意しておくことが望ましいでしょう。
多くのオール電化向けプランでは、夜間の電気料金が安く設定される代わりに、日中の料金が割高になる傾向があります。
そのため、日中に在宅して多くの電気を使用する家庭では、思ったほど経済的メリットが得られない可能性があるのです。
さらに、初期導入コストが高いという側面もあり、エコキュートやIHクッキングヒーターなどの設備は、ガス機器と比較すると高額な場合が多く、設置工事費も含めると初期費用はかさみます。
オール電化の電気代が高くなる3つの原因
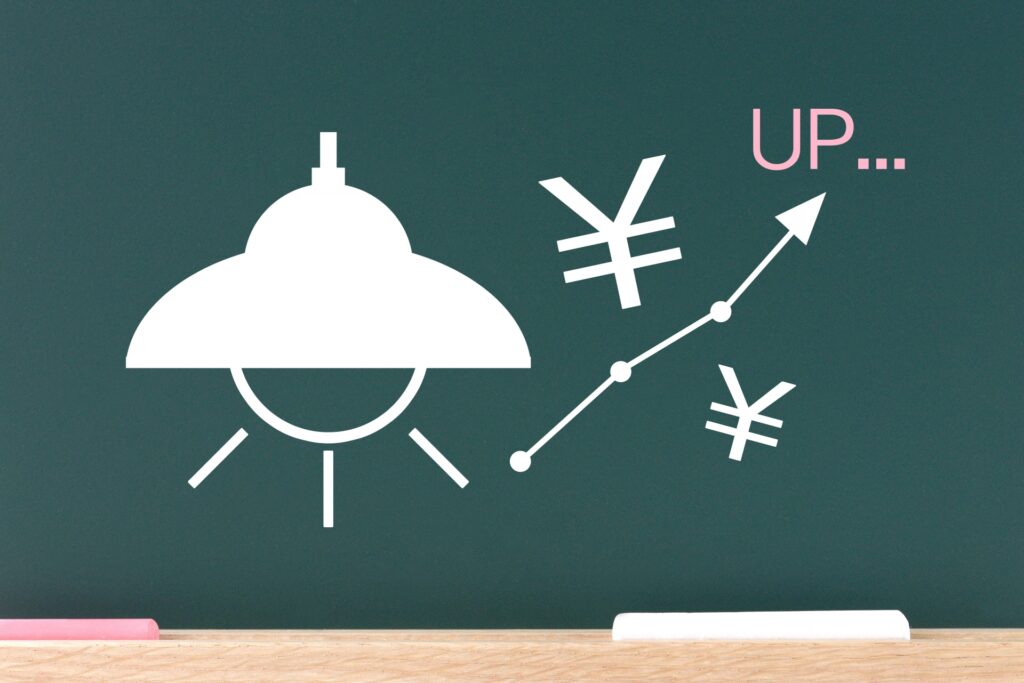
オール電化住宅で電気代が予想以上に高くなってしまう原因はいくつか考えられます。
これらの要因を把握することで、無駄な電気代の支払いを避けられるでしょう。ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
原因1:電気料金の高騰
近年の電気料金の高騰は、オール電化住宅の家計を直撃しています。
東京電力が発表している平均モデルの電気料金によれば、2016年9月には電気代が6,076円だったのに対し、2022年8月には9,118円まで上昇しました。
この約50%の上昇は、すべての家庭に影響していますが、特に電気に依存するオール電化住宅ではその影響が大きく表れます。
料金上昇の主な原因は、多くの原子力発電所の停止による電力不足です。また「円安による燃料輸入価格の高騰」といった国際情勢も大きく影響しています。
これらの要因は個人では対応が難しく、短期間での改善も見込めないため、この状況下での節約方法を考える必要があるのです。
原因2:料金プランと生活習慣の不一致
オール電化向けの電気料金プランと生活習慣のミスマッチも、電気代高騰の大きな原因となっています。
オール電化向けプランは一般的に深夜の電気料金が安く、日中は高く設定されています。例えば、東京電力の「スマートライフS」では、2024年1月の料金で深夜の午前1〜6時は1kWhあたり27.86円、日中は35.76円となっています。
しかし、日中在宅して多くの電気を使う家庭では、このプランのメリットを活かせません。
自分の生活リズムに合わないプランを選んでいると、電気代が必要以上に高くなってしまうのです。
原因3:旧型機器を使用している
古い電化製品を使い続けていることも、電気代を押し上げる大きな要因です。
1990年代に普及した「電気温水器」や「蓄熱暖房機」は、現在の最新機器と比べて消費電力が著しく多くなっています。
実際に、月の電気代が10万円を超えるオール電化世帯では、約70%が「蓄熱暖房機」による暖房、約20%が「電気温水器」による給湯だったという事例も報告されています。
これは旧式の機器が電気代を押し上げる主因となっていることを示しています。最新の省エネ機器に買い替えることで、大幅な電気代削減が期待できるでしょう。
オール電化住宅の電気代を節約する3つの方法

オール電化住宅の電気代を効果的に削減するには、いくつかの重要な対策があります。
以下の電気代節約の主な方法から自分の家庭に合った方法を選ぶことで、大幅な節約が見込めます。
これらの対策は初期投資が必要なものもありますが、長期的に見れば電気代を抑える有効な手段です。それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。
最新の省エネ機器へ買い替える
古い電化製品を最新の省エネ機器に買い替えることで、電気代を大幅に削減できます。
特に効果が大きいのは、給湯設備の更新です。古い電気温水器からエコキュートに買い替えると、給湯にかかる電気代を約75%削減できると言われています。
これは、エコキュートが空気中の熱を利用して効率よくお湯を沸かす仕組みになっているからです。
暖房機器についても同様で、旧式の蓄熱暖房機から最新のエアコンへの買い替えにより、約72%の電気料金削減が期待できます。
もちろん機器の買い替えには初期費用がかかりますが、電気代の節約分を考えると数年で元が取れることが多いでしょう。
最適な電力会社とプランを選ぶ
電力自由化により、オール電化向けプランを提供する電力会社が増えました。自分の生活スタイルに合った電力会社とプランを選ぶことが重要です。
まず確認すべきは、日中と夜間の電気使用量のバランスです。夜間に電気をたくさん使う家庭なら、夜間の電気料金が安いオール電化向けプランが適しています。
逆に日中の電気使用量が多い家庭では、時間帯別の料金差が小さいプランの方が有利かもしれません。
電力会社を選ぶ際は、基本料金と電力量料金の両方を比較することが大切です。
さらに、ポイント還元などの特典も含めて総合的に判断するのがよいでしょう。各社のウェブサイトや比較サイトを活用することで、自分に最適なプランを見つけられます。
太陽光発電や蓄電池を導入する
太陽光発電システムと蓄電池の導入は、長期的な視点で見ると大きな節約につながります。
太陽光パネルで発電した電気を自家消費することで、電力会社から購入する電気量を減らせます。さらに余った電気は電力会社に売却することも可能です。
蓄電池を併用すれば、さらに効率的です。日中に発電した電気を蓄電池に貯めておき、電気料金が高い時間帯に使用することで、電気代の削減効果を最大化できます。
また停電時のバックアップ電源としても役立つため、オール電化住宅のデメリットである停電時の脆弱性も克服できるでしょう。
導入費用は決して安くありませんが、国や自治体の補助金制度を活用することで負担を軽減できます。
また、設備の寿命である10〜20年の長期で考えると、多くの場合で導入コストを上回る節約効果が期待できるのです。
省エネ機器導入には支援制度を活用しよう

省エネ機器の導入には初期費用がかかりますが、様々な支援制度を活用することでその負担を軽減できます。
これらの制度は年度ごとに内容が変わることがあるため、最新情報を確認することが大切です。それぞれの制度について詳しく見ていきましょう。
国と自治体の補助金制度
省エネ機器の導入を後押しするため、国や自治体はさまざまな補助金制度を設けています。
国の制度としては、「給湯省エネ事業」があります。この制度では、ヒートポンプ給湯機やハイブリッド給湯機、エネファームの導入に対して一定額の補助金が交付されます。
地方自治体でも独自の補助金制度を実施しているところが多くあります。例えば、東京都や神奈川県などでは、省エネ設備の導入に対する補助制度があります。
補助額や対象設備は自治体によって異なるため、お住まいの地域の自治体ホームページで確認するとよいでしょう。
これらの補助金制度を利用する際は、申請のタイミングに注意が必要です。多くの場合、設備の購入前に申請する必要があり、予算に限りがあるため早めの行動が大切です。
電力会社によるサポート
各電力会社も、省エネ機器の導入を支援するさまざまなプログラムを提供しています。
北海道電力では「スマート電化リース」として、エコキュートや寒冷地向け暖冷房エアコン、IHクッキングヒーターなどのリースサービスを展開しています。
初期費用ゼロで設備を導入でき、月々のリース料を支払うことで負担を分散できるメリットがあります。
このようなサポートは期間限定であることが多いため、タイミングを逃さないよう注意が必要です。最新情報を電力会社のウェブサイトで確認することをお勧めします。
初期費用の負担を減らして省エネ機器を導入できれば、長期的な電気代の節約につながり、より快適なオール電化ライフが実現できるはずです。
オール電化向け電力会社選びの3つのポイント

オール電化住宅に適した電力会社やプランを選ぶことは、電気代節約の大きなカギとなります。
最適な選択をするためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
これらのポイントを一つずつ確認していくことで、自分の生活スタイルに最適な電力会社とプランを見つけられるでしょう。
供給エリアと対応プランの確認
電力会社選びの第一歩は、自分の住んでいる地域で利用できる会社とプランを確認することです。
電力自由化により多くの会社が参入していますが、すべての会社がすべての地域でサービスを提供しているわけではありません。同じ会社でも地域によって提供プランが異なる場合もあります。
エリア別に利用可能な電力会社は、比較サイトや各電力会社のウェブサイトで確認できます。
まずは郵便番号を入力するだけで、自分の地域で選べるオール電化向けプランが一覧で表示されるサービスを利用するとよいでしょう。
また、オール電化住宅向けのプランがない会社もあるため、必ずオール電化向けのプランがあるかどうかも確認する必要があります。
時間帯別料金のしくみを理解する
オール電化向けプランの最大の特徴は、時間帯によって料金が変わる点です。この仕組みを理解することが重要です。
一般的なオール電化向けプランでは、夜間の電気料金が安く、日中は高く設定されています。
地域や会社によって「夜間」の定義が異なる点も注意が必要です。東京電力の「スマートライフS」では午前1時〜翌午前6時、関西電力の「はぴeタイムR」では23時〜翌7時が夜間時間帯となっています。
また、休日割引があるプランも多いため、平日と休日の生活パターンに大きな違いがある家庭は、休日割引の有無も確認するとよいでしょう。
自分の電気使用パターンと照らし合わせて最適なプランを選びましょう。
事前に電気料金シミュレーションを行う
実際に電力会社やプランを変更する前に、電気料金のシミュレーションを行うことが重要です。
シミュレーションを行うには、過去の電気使用量のデータが必要です。可能であれば1年分のデータがあると、季節変動も含めて比較できるでしょう。
多くの電力会社や比較サイトでは、シミュレーション機能を提供しています。自分の電気使用量を入力するだけで、複数のプランの料金を比較できます。
この際、基本料金と電力量料金の両方を含めた総額で比較することが大切です。
これらの結果だけでなく、契約期間や解約金の有無、ポイント還元などの特典も含めて総合的に判断しましょう。短期的な安さだけでなく、長期的なメリットも考慮して選ぶことが重要です。
東京都で太陽光発電の導入を検討している方は『サンドリア』がおすすめ

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社サンドリア |
| 所在地 | 東京都千代田区神田錦町2-9 大新ビル3階 |
| 設立年月日 | 1998年2月13日 |
| 公式サイト | https://solar.sandoria.link/ |
オール電化住宅の電気代削減に効果的な太陽光発電の導入を検討するなら株式会社サンドリアが最適です。
関東エリアを中心に10,000件以上の施工実績を持ち、高い技術力と丁寧な対応で定評があります。
各家庭の生活スタイルや屋根の形状、日照条件に合わせた最適なシステム設計を提案し、アフターケアも万全です。
オール電化と太陽光発電の組み合わせで、さらなる電気代削減が可能になります。まずは無料シミュレーションで効果を確認してみてはいかがでしょうか。
以下の記事では、サンドリアの評判や口コミを詳しく紹介しているので、あわせて参考にしてください。
まとめ
オール電化住宅の電気代は世帯人数や地域、季節によって大きく変動します。
平均的には一般住宅より光熱費が安くなる傾向がありますが、電気料金の高騰や旧型機器の使用、不適切な料金プランの選択により予想以上に高くなることもあります。
効果的な対策としては、エコキュートなどの省エネ機器への買い替え、生活スタイルに合った電力会社・プランの選択、太陽光発電システムの導入が挙げられます。
また、各種補助金や電力会社のサポートプログラムを活用することで初期費用の負担も軽減できます。
適切な対策で快適なオール電化生活と電気代削減の両立が可能です。









