「二人暮らしを始めたら電気代が予想以上に高くなった…」
「一人暮らしの時より、どれくらい電気代が上がるの?」
このような疑問や悩みを抱えていませんか?二人暮らしの電気代は一人暮らしの約1.6倍になりますが、工夫次第で効率的に節約できるポイントがたくさんあります。
本記事では二人暮らしの電気代の全国平均や、季節・地域による違い、二人暮らしならではの効果的な節約方法や、家電ごとの省エネ活用術を紹介します。
電気料金が高騰している今だからこそ、二人で協力して取り組める具体的な節約術を身につけましょう。
なお、以下では東京都で太陽光発電の導入を検討している方に向けて当メディアおすすめの施工会社を紹介していますので、ぜひ一度チェックしてみてください。
二人暮らしの電気代平均は約11,000円
二人暮らしの電気代は、総務省統計局の2023年家計調査によると、全国平均で約11,000円です。
この金額は2021年まで9,000円台だったものが、2022年以降に1万円を超える水準に上昇しました。
背景には世界的なエネルギー価格の高騰があります。石油や天然ガスなどの化石燃料の価格上昇に伴い、電気代を構成する「燃料費調整額」が大幅に増加したのが主な要因です。
また、電気代高騰の影響を緩和するために実施されていた政府の負担軽減措置も2025年3月に終了することから、家計への負担がさらに増す見通しとなっています。
これからの二人暮らしでは、平均額を念頭に置きながら、効率的な電気の使い方を心がけることが大切です。
一人と二人暮らし、電気代は何が違う?

一人暮らしから二人暮らしになると電気代は確かに上がりますが、単純に2倍になるわけではありません。
二人暮らしならではの特徴を理解すれば、より効率的に電気を使用できます。
これらを知ることで、より効率的な電気の使い方につなげることができるでしょう。
一人暮らしと二人暮らしの電気代平均の比較
総務省の統計によると、一人暮らしの電気代平均は約6,726円です。
これに対して二人暮らしは10,940円となっており、約1.63倍の金額になっています。人数が2倍になっても電気代は2倍にはならないという傾向が見て取れるでしょう。
この差は、三人世帯や四人世帯になるとさらに顕著になります。三人世帯の電気代平均は12,811円で二人世帯から17.1%の増加、四人世帯では13,532円と三人世帯からわずか5.6%の増加にとどまっています。
つまり、世帯人数が増えるほど、一人当たりの電気代は下がる傾向にあるのです。
実際の増加率を見ると、一人暮らしから二人暮らしへの移行時が最も大きく約62.6%増加します。このことから、電気代は一人暮らしから二人暮らしになる時が最も大きく変化すると言えます。
二人暮らしだと一人あたりが安くなる理由
二人暮らしでは、一人あたりの電気代が一人暮らしより安くなります。これには主に二つの理由があります。
まず一つ目は、基本料金の分散効果です。電気料金は基本料金と従量料金で構成されていますが、基本料金は世帯単位で発生するため、二人で分担すれば一人あたりの負担は半分になります。
二つ目の理由は、共有スペースや家電の共同利用によるものです。リビングやキッチンなどの共有スペースの照明やエアコンは、一人で使っても二人で使っても基本的に同じ電力しか消費しません。
特にエアコン・冷蔵庫・照明器具などの電力消費量が多い家電を共有できることは、大きなメリットと言えるでしょう。
さらに工夫次第では、より一人あたりの電気代を抑えることも可能だと考えられます。
季節や地域で変わる二人暮らしの電気代

二人暮らしの電気代は一年を通じて一定ではなく、季節や居住地域によって大きく変動することがわかっています。この変動を理解すれば、自分たちの電気代が平均と比較して高いのか低いのかを正しく判断できるようになるでしょう。
これらの差異を知ることで、より現実的な家計管理や節約計画を立てることが可能になるはずです。以下で詳しく解説します。
冬に跳ね上がる電気代の季節変動
二人暮らしの電気代は季節によって大きく変動し、特に冬季に高額になる傾向があります。
総務省の2023年の家計調査によると、二人暮らしの月間電気代は1月で15,130円、2月で16,478円、3月で15,122円と冬場に最も高くなっています。これに対し、6月は8,262円、7月は7,788円と夏場は比較的低い数値となっています。
この季節変動の最大の原因は「室内外の温度差」です。冬季は外気温と設定温度の差が大きくなりやすく、エアコンなどの暖房器具がより多くの電力を消費します。
さらに冬は日照時間が短いため、照明を使用する時間も長くなるでしょう。これに加えて暖房シーズンは冷房シーズンより長い傾向にあるため、結果的に冬の電気代が高くなるのです。
地域別に見る電気代の差と原因
二人暮らしの電気代は地域によっても大きく異なります。
総務省の2023年の家計調査によると、二人以上の世帯では北陸・東海地方が最も高く月平均約14,154円、次いで北海道・東北地方が約14,040円、中国・四国地方が約13,845円となっています。
一方、電気代が比較的安いのは九州・沖縄地方の約10,783円や近畿地方の約11,088円です。
この地域差が生じる主な要因は気候条件です。北海道・東北地方や北陸地方は冬の寒さが厳しく、暖房器具の使用頻度や稼働時間が長くなります。また雪国では日照時間も短いため、照明の使用も増えるでしょう。
このような地域特性を理解することで、自分たちの住む地域の平均電気代と比較でき、より現実的な節約目標を設定することが可能になります。
二人暮らしで電気代が高くなる3つの理由
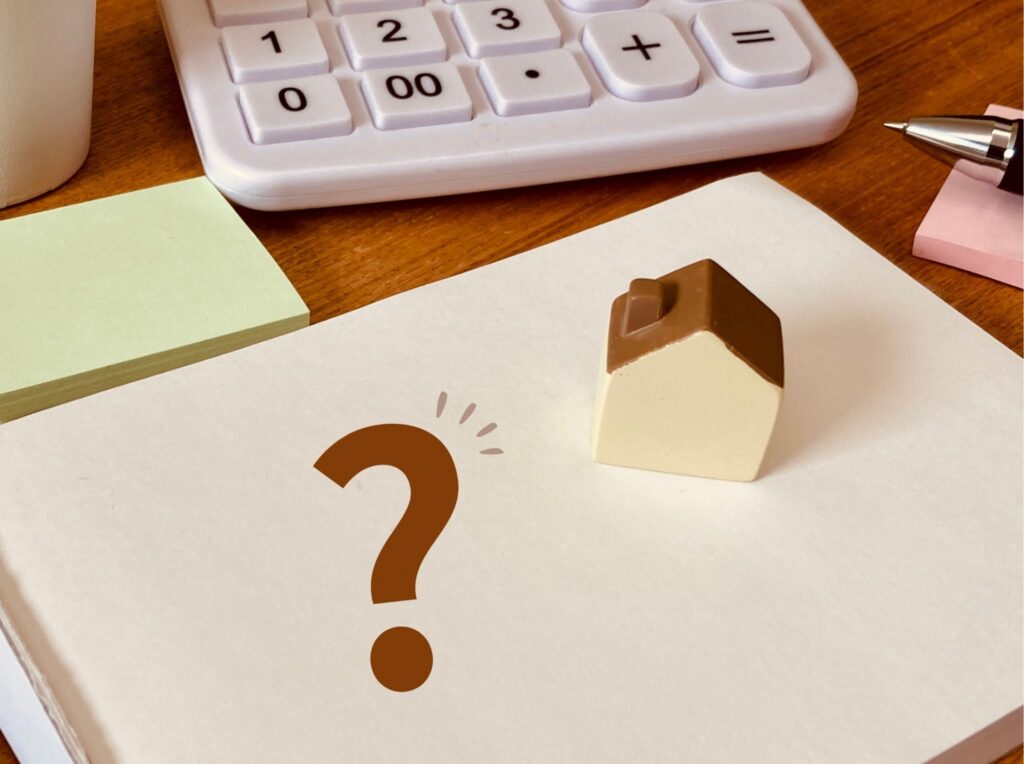
二人暮らしの電気代が予想以上に高くなってしまう背景には、生活パターンや家電の使い方に関する特有の要因があります。これらを理解することが、効果的な節約の第一歩となるでしょう。
これらの理由を把握し対策を講じることで、無理なく電気代を抑えることが可能です。
理由1:別々の部屋で電気を使う
二人暮らしで電気代が高くなる最も大きな理由の一つが、それぞれが別々の部屋で過ごす時間が多いことです。
二人が別の部屋にいると、照明やエアコン、テレビなどの家電を2台分同時に使用することになります。
例えば、一人がリビングでテレビを見ながらエアコンをつけ、もう一人が寝室でパソコンを使いながら別のエアコンを使用する状況は珍しくありません。この場合、エアコン2台分の電気代がかかることになるのです。
照明についても同様で、2部屋分の電気を点けることになれば、当然電気代は増加します。
特に冬場は暖房と照明の使用が重なるため、別々の部屋で過ごすことによる電気代の差は一層顕著になるでしょう。
理由2:在宅時間の違いが生む電気使用量増加
二人の生活リズムや仕事のスタイルが異なると、家での在宅時間にずれが生じます。このずれが電気使用量を増加させる原因となるのです。
例えば、一方が在宅勤務で日中も家にいる場合、もう一方が外出していても照明やエアコン、PCなどの電気製品を使用します。
さらに帰宅時間が異なると、食事の準備を別々にすることになり、電子レンジやIHクッキングヒーターなどの調理家電を複数回使用することになります。
また休日のずれも影響します。休日が異なれば、各々の休日に電気を使うため、結果的に電気を使用する日数が増えます。
こうした生活リズムの違いが、気づかないうちに電気代を押し上げている可能性は高いでしょう。
理由3:節電意識の温度差
二人の間で節電に対する意識や習慣に差があると、一方が節約しても効果が半減してしまいます。これも二人暮らしならではの電気代上昇の要因です。
例えば、一方は使わない部屋の電気をこまめに消す習慣があっても、もう一方にその習慣がなければ、結局は電気がつけっぱなしになります。
エアコンの設定温度についても、一方は省エネを意識して夏は28度、冬は20度に設定しても、もう一方が暑さ寒さに敏感で温度を調整してしまえば節約効果は得られません。
このような節電意識の違いは、思った以上に電気代に影響を与えるものです。お互いの節電に対する考え方を尊重しながらも、共通のルールを設けることが大切でしょう。
二人暮らしの電気代を節約する3STEP

二人暮らしの電気代を効果的に節約するには、契約内容の見直しから日常の使い方まで体系的に取り組むことが重要です。
以下の3つのステップを順番に実践することで、無理なく電気代を削減できるでしょう。
これらのステップは、一人ではなく二人で取り組むからこそ効果が高まります。二人の生活スタイルや価値観を尊重しながら、協力して電気代節約に取り組んでいきましょう。
STEP1:適切なアンペア数の選択
二人暮らしの場合、アンペア契約は30〜40Aが一般的ですが、実際の電気使用状況に合わせた最適なアンペア数を選ぶことが大切です。
例えば、東京電力の場合、30Aから20Aに下げると基本料金は月々約590円の節約になります。しかし同時に電子レンジとドライヤーを使うとブレーカーが落ちる可能性があるため、生活スタイルに合わせた選択が必要です。
アンペア数の選び方は、よく使う家電の消費電力を確認し、同時に使用する家電の合計ワット数を計算するのがポイントです。
10アンペアで約1,000W、20アンペアで約2,000Wの電力を使用できると考えれば、二人の生活に必要なアンペア数が見えてくるでしょう。
STEP2:電気料金プランの見直し
二人暮らしのライフスタイルに合った電気料金プランを選ぶことで、大幅な節約が可能になります。
2016年の電力自由化以降、各電力会社は様々なプランを提供しているため、自分たちの生活パターンに合ったものを探しましょう。
例えば、共働きで日中は不在が多い家庭なら、夜間の電気代が安い「時間帯別プラン」が有利かもしれません。
また、電気とガスをセットで契約すると割引が適用される「セット割」も検討価値があります。
プラン選びのポイントは、過去の電気使用量データを確認し、いつ・どれだけ電気を使っているかを把握することです。
多くの電力会社はウェブサイトでシミュレーションツールを提供しているので、自分たちの使用パターンを入力して最適なプランを見つけられるでしょう。
STEP3:節電意識の共有と協力体制の構築
二人暮らしで電気代を効果的に節約するには、お互いの節電意識を共有し、協力体制を築くことが欠かせません。まずは二人で話し合い、無理のない範囲で節電ルールを決めることから始めましょう。
具体的なルール例としては「使わない部屋の電気は消す」「長時間使わない家電はコンセントを抜く」などが挙げられます。こうしたルールは二人の合意のもとで決めることが大切です。
また月々の電気代を二人で確認し、節約の成果を共有することも継続のコツです。
「先月より○○円減った」といった成果を実感できれば、節電へのモチベーションも高まるでしょう。
電気代削減を競争ではなく、二人の共通目標として捉えることで、楽しみながら続けられる習慣になります。
二人暮らしの家電別省エネ活用術

家庭の電気代の大部分を占めるのは主要家電の使用によるものです。二人暮らしならではの家電の効率的な使い方を知ることで、快適さを保ちながら電気代を削減できます。
これらの家電は生活に欠かせないものですが、使い方を少し工夫するだけで大きな節約効果が得られます。二人で協力して取り組むことで、さらに効果を高められるでしょう。
エアコンの賢い使い方
エアコンは家庭の電気使用量の約15%を占める大きな電力消費源です。二人暮らしでは、適切な温度設定と使用方法で大幅な節約が可能です。
まず室温設定は、夏は28℃、冬は20℃を目安にしましょう。設定温度を夏は1℃上げると約13%、冬は1℃下げると約10%の節電になります。二人の快適温度が異なる場合は、少し厚着や薄着で調整すると良いでしょう。
またフィルター掃除は月に2回を目安に行います。フィルターが目詰まりすると冷暖房効率が下がり、最大で50%も余計な電力を消費します。二人で当番制にして定期的に掃除すれば負担も半減です。
扇風機やサーキュレーターとの併用も効果的です。室内の空気を循環させることで、設定温度を変えずに体感温度を調整できます。
冷蔵庫の効率的な運用方法
冷蔵庫は24時間稼働し続ける家電で、電気使用量の約14%を占めています。二人分の食材をしっかり保存しながらも電気代を抑える工夫をしましょう。
詰め込みすぎは禁物です。冷蔵室の食品は7割程度の量に抑え、冷気の循環を妨げないようにします。
一方で冷凍室は逆に8割程度まで詰めると、食品同士が冷やし合って効率が良くなります。
開閉回数も重要なポイントです。開閉を10回から5回に減らすだけで約20%の節電効果があります。二人で冷蔵庫の中身を共有し、「何がどこにあるか」を把握しておくと、ドアの前で迷う時間も減らせます。
二人の食生活を話し合い、必要な食材だけを計画的に購入・保存することで、冷蔵庫の効率が高まります。
共有スペースの照明・家電活用法
リビングやキッチンなどの共有スペースでは、照明やテレビなどの電気代を工夫次第で大きく削減できます。
照明はLED電球への交換が最も効果的です。従来の白熱電球と比べて約80%の節電になります。二人の生活リズムに合わせ、必要な場所だけを照らす「部分照明」も有効でしょう。
テレビは画面の明るさを控えめにし、視聴しないときはこまめに電源を切ります。「ながら見」をやめるだけでも約2%の節電効果があります。
共有スペースでの家電使用時間を調整することも大切です。二人が同じ時間帯に同じ部屋で過ごせるよう工夫すれば、部屋数分の電気を使わずに済みます。
休日は二人で同じ部屋で過ごす時間を増やすなど、生活リズムを少し合わせるだけでも効果は大きいでしょう。
洗濯機・乾燥機を効率化する方法
洗濯機や乾燥機は二人分の衣類をまとめて洗うことで、効率的に使用できます。
洗濯は一回の量を増やして回数を減らすのが基本です。洗濯機を4割の量で2回使うより、8割の量で1回使う方が年間約4,000円も節約できます。
また洗濯のすすぎ回数を2回から1回に減らすと、約17.5%の節電になります。最近の洗剤は「すすぎ1回」対応のものも多いので、活用してみてください。
乾燥機は電気代がかかるため、天気の良い日は極力自然乾燥を活用しましょう。やむを得ず使用する場合は、脱水をしっかり行い、乾燥時間を短縮する工夫が有効です。
二人のスケジュールを調整し、効率的な洗濯計画を立てることも大切でしょう。
戸建て住宅なら太陽光発電で電気代を削減しよう

二人暮らしで戸建て住宅にお住まいの方は、太陽光発電システムの導入も有効な選択肢です。初期投資は必要ですが、長期的に見れば大幅な電気代削減が期待できます。
発電した電気を自家消費することで、電力会社から購入する電気量を減らせるほか、余った電力は売電することも可能です。
特に在宅時間が長い二人暮らしなら、昼間の発電電力を効率的に活用できるでしょう。
また蓄電池と組み合わせれば、さらに自給自足率を高められます。環境にも優しく、将来的な電気代高騰リスクへの備えにもなります。
東京都で太陽光発電の導入を検討している方は『サンドリア』がおすすめ

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社サンドリア |
| 所在地 | 東京都千代田区神田錦町2-9 大新ビル3階 |
| 設立年月日 | 1998年2月13日 |
| 公式サイト | https://solar.sandoria.link/ |
太陽光発電システムの導入を検討するなら、実績豊富な株式会社サンドリアがおすすめです。
関東エリアを中心に10,000件以上の施工実績を持ち、各家庭の屋根形状や日照条件に合わせた最適な設計を提案してくれます。
施工後も定期点検や緊急時対応など長期的なサポート体制が整っているため安心です。
太陽光発電で電気代を削減したい二人暮らしの方は、まずはサンドリアに相談してみるとよいでしょう。
以下の記事では、サンドリアの評判や口コミを詳しく紹介しているので、あわせて参考にしてください。
まとめ
二人暮らしの電気代平均は約11,000円ですが、季節や地域によって大きく変動します。
特に冬季は平均16,000円を超える月もあり、寒冷地では電気代が高くなる傾向があります。
効果的な節約には、適切なアンペア数の選択、電気料金プランの見直し、二人での節電意識の共有という3ステップが有効です。
二人で協力して電気の使い方を見直せば、快適な生活を維持しながらも、電気代を効果的に節約できるでしょう。









